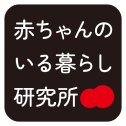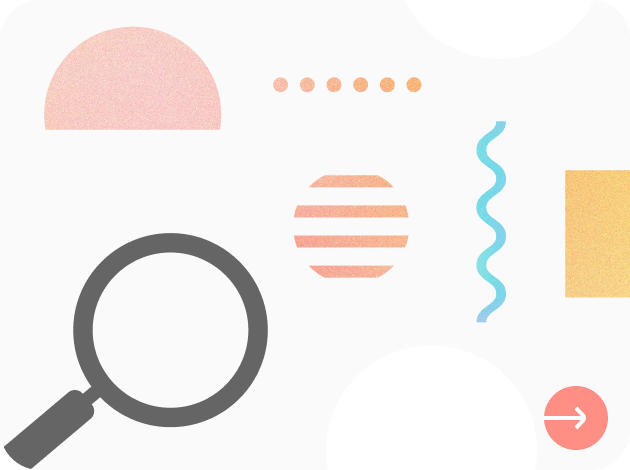子育て費用、どうしてる?教育費の準備は?

妊娠、出産を機に子育て費用について考える方も多いのではないでしょうか。「児童手当はいくらもらえるの?」、「教育費はどれくらい必要?」など、具体的な金額から始まり「どうやって用意したらいいの?」、「結局みんなどうしているの?」といったノウハウまで、知りたいことは盛りだくさん。赤ちゃんのいる暮らし研究所では、株式会社セブン銀行と共同で妊娠中から4歳までのお子さまがいらっしゃる方を対象に、おかねについてのアンケートを実施しました。なかなか聞けない他のご家庭のおかねの話、お役立ていただけると幸いです。
目次
■4人に1人はパートナーとのコミュニケーションに不満
おかねの管理の仕方はさまざまですが、みなさんは今の管理に満足しているのでしょうか。現在のおかねの管理への満足度を聞いてみると、およそ4割の方が「すこし不満・不満」と回答しました。

「すこし不満・不満」と回答した方に不満に感じている内容を聞いてみると、半数以上の方が「もっといい方法があるかもしれないが、わからない」と回答していました。また、4人に1人は配偶者・パートナーと家庭のおかねの状況を話しにくいと感じており、コミュニケーションがうまく取れていないことも不満につながっているようです。アンケートは複数回答できるようになっていましたので、実際には複数のお悩みをお持ちの方もいらっしゃると考えられます。
次に、ご家庭でのおかねの管理はどなたがされているのかをうかがいました。

お子さまの年齢が上がるにつれて共同で管理している方が減っていき、1人で管理している方が増える傾向が見られました。お子さまの成長に伴って、家庭内での役割分担が変化していくようです。
お仕事をされているかどうか、産休・育休中かどうかでご自身とパートナーとの収入バランスも変わりますし、家事・育児もお子さまの成長によって内容が変わっていきます。そうした変化があるからこそ、おかねに関することも含めてこまめにコミュニケーションをとっておきたいですね。
■出産祝い、回答者の4割が子育て費用に使用
回答いただいた方のご家庭では、お子さまのためのおかねをどのように管理しているのでしょうか。一例にはなりますが、出産祝いについてご紹介します。

およそ4割の方が、出産祝いは出産・育児で必要なものに使っていると回答しました。一方で、お子さま名義で貯蓄をしている方も3割程度いらっしゃいました。いずれも「お子さまのために」という想いは同じようです。
■お子さま名義の銀行口座は7割が開設/検討

貯蓄の方法として出てきた「お子さま名義の銀行口座」を開設している人は50%でした。これから開設予定という方も含めると、7割近くにのぼります。
お子さま名義の銀行口座の使い方についてアンケートに寄せられたお声を見ていると、出産祝いだけでなくお子さまにいただいたお年玉やお小遣いなどを生活費とは分けて貯めておき、成長したら渡したいと思っている方が多いことがうかがえました。また、こんな使い方をした、という声も。

お子さま名義だからこそできるすてきな使い方で、将来振り返る時にも楽しめそうですね。
■教育費の準備方法、「児童手当の貯蓄」が最多
お子さまが成長する中でまとまった金額が必要になるのは、やはり教育費ではないでしょうか。文部科学省の調査では、令和3年度の平均的な費用は幼稚園から高校まですべて公立で574万円、すべて私立では1,838万円となっていました。(文部科学省,2022年)大きな金額なので、多くの人にとってはすぐに用意できるものではありません。時間をかけてコツコツと用意していけると安心です。では、みなさんどのように準備をしているのでしょうか。

教育資金の準備方法では、児童手当を貯蓄している方が多いようでした。また、積み立てNISAを利用している方も2割程度いらっしゃいました。
多くの方が貯蓄している児童手当ですが、どれくらいの金額が用意できるのでしょうか。2025年の支給条件を基に年間の給付金額を計算してみました。

給付期間は高校生年代(18歳に到達後、最初の3月31日)までとなっており、お子さまの生まれた月によって受け取りの総額は変動します。また、受給に必要な申請が遅れると受け取れる期間が短くなってしまうことにも注意が必要です。将来の進学費用として貯蓄する方法もありますし、現在のお子さまの暮らしや教育に活かす、という方法もありますね。
■教育費の準備は妊娠中から検討がオススメ

教育費の準備を検討された方のうち、51%が妊娠中に検討を始めていました。また、実際に準備を始めた時期で最も多かったのは0歳台でした。妊娠中から検討はしているものの、実際に準備を始めるのはお子さまが生まれてから、という方が多いようです。
産後はお子さまのお世話が忙しく、まとまった時間が取りづらくなってしまうので、情報収集はなるべく妊娠中に進めておくと良さそうです。どうやって教育費を準備していくか妊娠中に計画を立てておけば、忙しい産後でもスムーズに教育費の準備を始められそうですね。
児童手当の内容や高校授業料の無償化など、子育て支援策は変化していきます。今の情報を収集して準備するだけでなく、今後の変化についてもチェックしていくことが必要です。また、お子さまが入園・入学するなどの節目のタイミングで、教育費の準備状況を見直してみると良いかもしれません。
アカチャンホンポでは各自治体の子育て情報が検索できるページをご用意しています。
いかがでしたでしょうか。おかねのことは周囲にはなかなか聞きづらいものですが、もしものときや将来の大きな出費に備えて、できる範囲で準備しておけると安心ですね。
〈調査概要〉
調査期間:2024年9月20日(金)~9月23日(月)
調査方法:インターネット調査
実施機関:株式会社セブン銀行と赤ちゃんのいる暮らし研究所による共同実施
対象:18~49歳のアカチャンホンポ会員
有効回答数:818件
関連キーワード