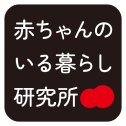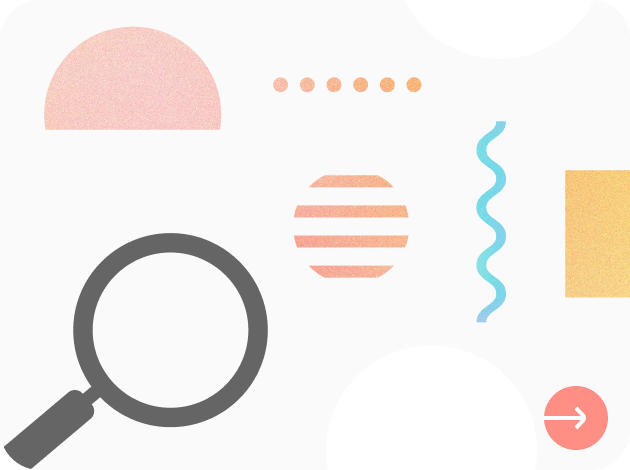出産施設選び、通いやすさ以外の注目ポイントは?

出産施設は、初めて赤ちゃんと会える場所。そして、おうちでの赤ちゃんとの暮らしに向けて準備をしたり、ママが出産直後の身体を休めたりする場所でもあります。どんなところがいいかな?何を見て選べばいい?気を付けたほうがいいことは?などいろいろと気になる方も多いのでは。実は、出産施設選びには自宅や里帰り先からの通いやすさの他にも注目したいポイントがあるようです。今回は、お子さまを2人ご出産されたママ4名に出産施設選びについてお話を伺いました。1人目の出産のときに気づいたこと、2人目のときに活かしたことなど、先輩ママの声をお届けします。
目次
■通いやすさ以外で気にされていたのは、夜間の対応と個室の有無
2025年8月に公開した当社「先輩たちのリアルをお届け!人それぞれのマタニティLIFE」サイトの記事では、出産施設選びで重視した項目の1位を「自宅などからの通いやすさ」とご紹介しました。赤ちゃんのいる暮らし研究所では、同じアンケートをお子さまの人数が「1人の方」、「2人以上の方」でグループ分けし、重視した項目の違いを確認しました。すると、「夜間の預かりやミルクでの授乳の頼みやすさ」に最も差が見られました。
夜間に赤ちゃんを新生児室で預かってもらえたり、その間の授乳をさく乳した母乳やミルクで対応してもらえると、ママは睡眠時間をとりやすくなり、身体を休めることもできます。赤ちゃんと一緒に過ごすことと預けること、どちらも状況に応じて選べる体制が整っていると安心です。

また、インタビューに参加いただいた4名全員が2人目の出産では個室を選び、「個室にしてよかった!」と回答しました。

1人目出産後の入院中は相部屋で過ごしたものの、周りを気にしてリラックスできなかったため2人目の出産では個室を選ぶ、という方もいるようです。個室があるかどうか、金額がどの程度変わるのか、というのも出産施設によって違うため、個室を希望する場合は事前に確認しておきましょう。
■決める前にパートナーと話そう。立ち会い出産、どうする?

立ち会い出産をしたいかどうかは人それぞれ。まずは自分とパートナー、それぞれがどうしたいのか、パートナーとしっかり話しておきましょう。また、立ち会いを希望するか・しないか以外にも、話しておいた方がいいこともあります。立ち会いを希望する場合、深夜の出産だったらどうする?里帰り先まで来ることができる?平日だったら仕事はどうする?立ち会いを希望しない場合、出産後にどう連絡する?病院に持ってきて欲しいものがあったらどうしよう?など、さまざまなシチュエーションを考えておくと安心です。
■2人目以降の出産では「子ども連れでの通いやすさ」も大事

上のお子さまがいる場合、健診時に病院に連れていけるかどうかも注意したいポイントです。キッズスペースなどの設備が病院にあっても、待ち時間が長いと上のお子さまを連れて行きにくい場合があります。また、通院のための交通手段ではこんな声もありました。

妊娠前は自分で車を運転して行けた場所でも、妊娠するとつわりで体調が悪くなるなど、自分で運転して行くことが難しくなることもあります。車以外の交通手段でも通院が可能かどうか、その場合、お子さま連れでも移動できるかどうかも確認しておくことがオススメです。
また、産後の入院中は上のお子さまのお世話をどうするのかも考える必要が出てきます。誰が、どこで、どんなお世話をするのか。パートナーと相談し、必要なお世話の内容を確認したり、手伝ってもらいたい内容を周囲の協力者にしっかり伝えておくなど準備をしておきましょう。行政のサポートサービスへの登録や、冷凍幼児食のストック、家事代行サービスなどを検討してもいいかもしれませんね。
出産施設選びには通いやすさだけでなく、さまざまなポイントがあることを想像していただけたでしょうか。今回ご紹介した内容だけでなく、気になることは出産施設に確認しておくと安心ですね。今回ご紹介した内容が、みなさまの参考になれば幸いです。
<インタビュー概要>
調査期間:2025年7月4日(金)
調査方法:対面でのグループインタビュー
実施機関:赤ちゃんのいる暮らし研究所
対象:出産経験のある女性従業員
インタビュー人数:4名
<アンケート概要>
調査期間:2025年6月6日(金)~6月12日(木)
調査方法:インターネット調査
実施機関:株式会社 赤ちゃん本舗
対象:アカチャンホンポ会員
有効回答数:4,777件
関連キーワード